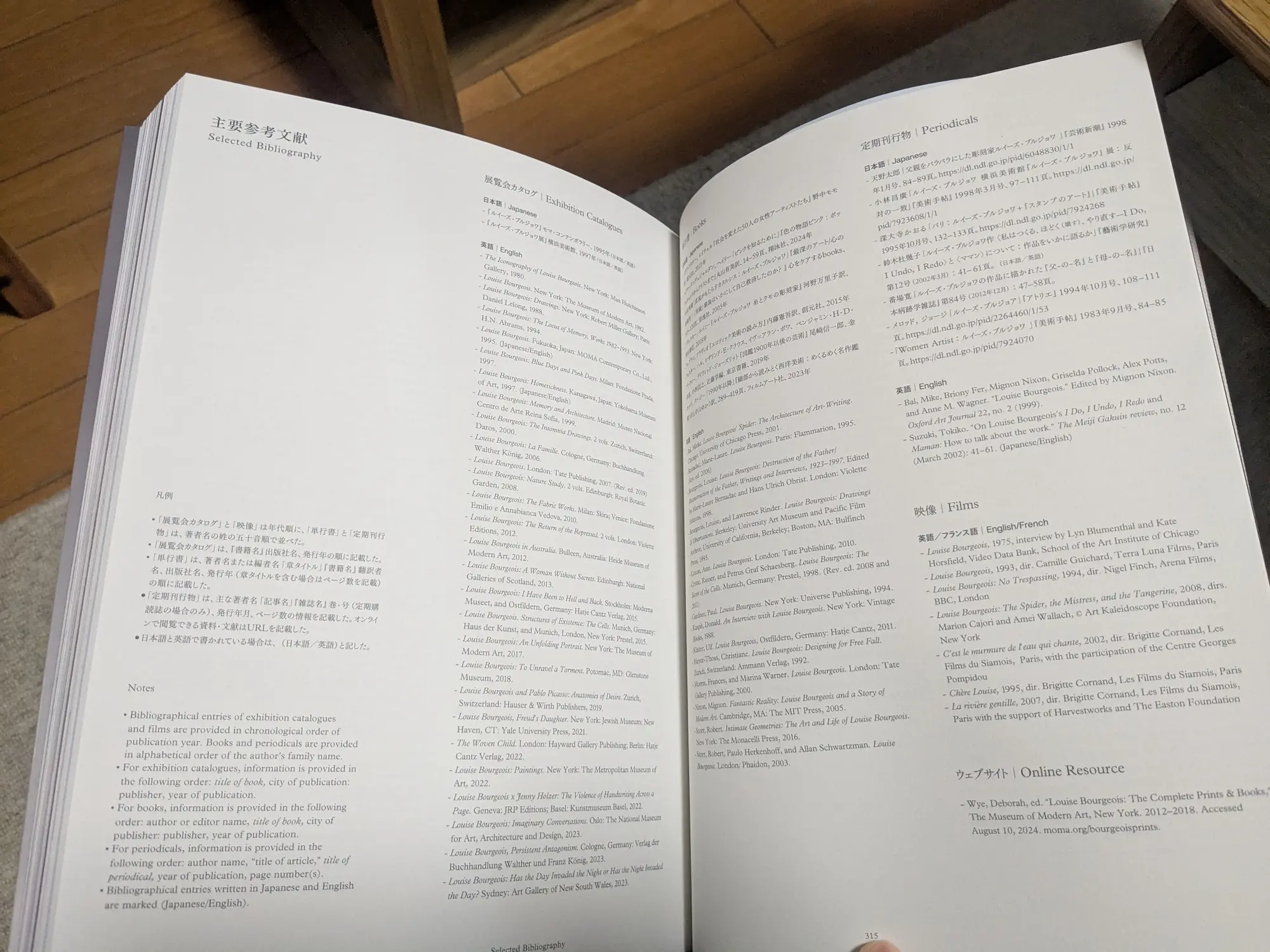ブルジョワのオレンジの映像見たとき、こんなに誠実に怒り続けられるんだってことがむしろすごいとおもった、直接父親に言われなかったとしても、あの気まずさは多くの少女に心当たりあるというか、「お前にはペニスがないから美しくない存在だ」ってメッセージをあらゆる場面で受け取ることもよくあることであって、
でもそういう恥辱から目を逸らさないのも技術だなあ。。
軍人が不当な命令を拒否する権利【寄稿】
https://japan.hani.co.kr/arti/opinion/52070.html
”ベトナム戦争に参戦した軍人の1人が勇気を出し、2022年にソウル中央地方裁に証人として出廷した。「証人は、国際人道法や戦争法の教育を受けたことがありますか」「ありません」「証人は、非武装の民間人を攻撃することが国際法違反だという事実を、教育されたことがありますか」「ありません」。教育の不在は、当時の悲劇の原因の一つだった”
年始の読書、『戦国の村を行く』『対馬の海に沈む』の次はこちら。
Futuress『デザインはみんなのもの』井上麻那巳訳、Troublemakers Publishing
https://troublemakersmag.square.site/product/design-is-for-everybody/5
【オリジナルステッカー1枚付き】
どうしてデザイン賞の審査員や受賞者は男性ばかりなの? どうして欧米でデザインを学んだことがステータスになるの? どうしてスマートフォンは女性の手には大きすぎるの?
スイスを拠点にするグローバルなフェミニスト・コミュニティ「Futuress」が掲載してきた、「フェミニズム × デザイン」の視点で身近なデザインの、わたしたちの社会の当たり前を問い直す5本のエッセイを収録。トルコ、ノルウェー、アメリカ、インド、パレスチナ。世界のフェミニストたちから届いた、希望と連帯のストーリー。
たとえば、父からペニスの欠如をからかわれるという体験は、「父との葛藤」として表象されるというより、「女性として社会化されていることへの屈辱」というより広い文脈に接続できるけど、ブルジョワ個人の物語に還元されることで、こういった文脈が捨てられる。個別具体的な父と子の関係の問題ではないんだけど、そういうのを無視するストーリーテリングになっていて、けっこうひどいと感じる。
この記事に書かれている少女時代に父からペニスの欠如を言われ周囲から笑われたというエピソード、衝撃的であると同時にある意味凡庸なものでもあって、それはこの手の経験をしている人はそれなりにいると思われるからなんだけど、しかしこの経験を意味ある経験に変換しているのはルイーズ・ブルジョワが優れたアーティストであるからであって、彼女の構造化能力がなければこのトラウマ経験は忘れられる種類のものだとおもう。創作によってトラウマが回帰し呼び出されているのであって、トラウマが創作に向かわせたわけではない。
こういう読み方の問題は、作品のなかにブルジョワ本人の病理を読みとらせようとすることにあるけど、芸術作品を病理的な表出として語るのってもう数世代も前の話じゃないかとおもう。ブルジョワのなかに病理を見出そうとすれば、自分の立ち位置を健常者とみなすことで規範の強化をすることになる。ブルジョワは「正しい家族のありかた」から外れているから強い芸術的表出につながる、という誤った観念が導かれてしまう(前の投稿で参照した中野信子の見解はほとんどこの誤った観念で述べられているようにしか見えない、愛着障害があったのでは?とかなにを根拠にという感じだ)。
https://hillslife.jp/art/2024/12/02/louise-bourgeois/